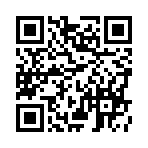きっかけづくり講座レポート③
『ここにはプログラムはありません。だから、子どもは遊ぶんです。』
“冒険遊び場”って聞いて最初は、木にロープをくくって、
ターザンのように『あ~あ あ~』なんていうのを想像してたんですが、違いました。
冒険遊び場(プレーパーク)では、
廃材で何か作って遊ぶ!リアカーにいっぱい乗って遊ぶ!

ベッコウ飴を作る!自由に料理する!・・・・・
たき火を囲んで、ただボーっとしている。ひたすら話をしている!などなど

大人から見たら、しょうもない。何の意味もないようなことを
子どもたちが、自分たちのペースで遊びたいように遊んでました。
でも、中には、むっちゃ面白そうなこともあって、
一緒に混ぜてもらったりもしました
と『たごっこパーク』視察隊からの報告。
とにかく、冒険遊び場には、自由に遊べる“雰囲気”があって
○○づくりとかいったプログラムがなく、まったりした居心地がいい空間。
プログラムがないから、遊びがどんどん変化して展開していくらしいんです。
そこが、面白いところなんだと。
そのほかにも、子どもだけでなく、大人にとっても
子どもと遊ぶ・しゃべる・教わる・つくるといった時間や
一緒に集まるお母さんや近所のお兄ちゃんとの会話も楽しみだったり、
スタッフとして参加する地域の人からも
子どものイキイキした姿が、私たちのエネルギー源!なんて報告も。
冒険遊び場の様子をみて、いろんな魅力が遊び場づくりに含まれてるなと感じました。
実際に活動したくてうずうずしてまーす
つづきは、冒険遊び場での大人の役割です。 by ブライアン
『ここにはプログラムはありません。だから、子どもは遊ぶんです。』
“冒険遊び場”って聞いて最初は、木にロープをくくって、
ターザンのように『あ~あ あ~』なんていうのを想像してたんですが、違いました。
冒険遊び場(プレーパーク)では、
廃材で何か作って遊ぶ!リアカーにいっぱい乗って遊ぶ!

ベッコウ飴を作る!自由に料理する!・・・・・
たき火を囲んで、ただボーっとしている。ひたすら話をしている!などなど

大人から見たら、しょうもない。何の意味もないようなことを
子どもたちが、自分たちのペースで遊びたいように遊んでました。
でも、中には、むっちゃ面白そうなこともあって、
一緒に混ぜてもらったりもしました

と『たごっこパーク』視察隊からの報告。
とにかく、冒険遊び場には、自由に遊べる“雰囲気”があって
○○づくりとかいったプログラムがなく、まったりした居心地がいい空間。
プログラムがないから、遊びがどんどん変化して展開していくらしいんです。
そこが、面白いところなんだと。
そのほかにも、子どもだけでなく、大人にとっても
子どもと遊ぶ・しゃべる・教わる・つくるといった時間や
一緒に集まるお母さんや近所のお兄ちゃんとの会話も楽しみだったり、
スタッフとして参加する地域の人からも
子どものイキイキした姿が、私たちのエネルギー源!なんて報告も。
冒険遊び場の様子をみて、いろんな魅力が遊び場づくりに含まれてるなと感じました。
実際に活動したくてうずうずしてまーす

つづきは、冒険遊び場での大人の役割です。 by ブライアン
「子どもが外で遊べない、遊ばない」、「子どもの外遊びが減っている」
と言われる問題について、
「三間(空間・時間・仲間)がない」ということがよく言われています。
子どもが遊べる場所が減ってきたり、
塾やお稽古で遊ぶ時間がなかったり、
近所に子どもが少なかったりということですね。
先日の「冒険遊び場作りきっかけ講座」の分団協議の中では、
親が子どもの遊びを制限してしまっているのではないか,
という指摘がありました。
危ないことや汚いことはさせなかったり、
事なかれ主義で子ども同士のやり取りをリードしていたりして、
子どもの遊びは管理されている状態であること、
親同士のつながりがないために,子ども同士を遊ばせにくかったりすることです。
それらのように、外で遊ぶことを制限する要因があるのと同時に、
子どもを室内遊びにひきつけるものがあるのでしょう。
たとえば、テレビゲームや携帯ゲーム。
私の子ども時代は外でハチャメチャに遊ぶことが多かったけれど、
外ばかりで遊んでたというわけではなく、
友だちの家にあがってファミコンもよくしていました。
それはそれで、やっぱり面白かったです。
子どもの遊びの中心がテレビゲームや携帯ゲームになるのも、わからなくもないです。
外遊びが減り、圧倒的に室内遊びが増えたということについて、
子どもについての評論を多数書かれている斎藤次郎さんは、
次のように言っています。
「僕の子どもの時代は、毎日暗くなるまで遊んでいました。
もちろん遊びたくって遊んでたんですけど、家にいたって、ろくな事はないんです。
親に用を言いつけられるか、勉強しろって言われるでしょう。
それに、おやつらしいものがあるわけでもない。
僕と同じ境遇の友だちはいっぱいいて、自然に群れになるんです。
だけどいまの子どもは冷蔵庫を開ければおやつはあるし、母はあまり文句は言わないし、
自分の部屋にいれば何をしてもわからないし、テレビもファミコンもあるし、
これでなお外に出て遊ぶなんて、
何でわざわざという感じになるんじゃないかなあ」
いまの子どもたちに、わざわざ外に出て友だちと群れて遊ぶ面白さを、
いっぱい体験させてあげたいなあと思っています。
by あかちゃんせんせい
と言われる問題について、
「三間(空間・時間・仲間)がない」ということがよく言われています。
子どもが遊べる場所が減ってきたり、
塾やお稽古で遊ぶ時間がなかったり、
近所に子どもが少なかったりということですね。
先日の「冒険遊び場作りきっかけ講座」の分団協議の中では、
親が子どもの遊びを制限してしまっているのではないか,
という指摘がありました。
危ないことや汚いことはさせなかったり、
事なかれ主義で子ども同士のやり取りをリードしていたりして、
子どもの遊びは管理されている状態であること、
親同士のつながりがないために,子ども同士を遊ばせにくかったりすることです。
それらのように、外で遊ぶことを制限する要因があるのと同時に、
子どもを室内遊びにひきつけるものがあるのでしょう。
たとえば、テレビゲームや携帯ゲーム。
私の子ども時代は外でハチャメチャに遊ぶことが多かったけれど、
外ばかりで遊んでたというわけではなく、
友だちの家にあがってファミコンもよくしていました。
それはそれで、やっぱり面白かったです。
子どもの遊びの中心がテレビゲームや携帯ゲームになるのも、わからなくもないです。
外遊びが減り、圧倒的に室内遊びが増えたということについて、
子どもについての評論を多数書かれている斎藤次郎さんは、
次のように言っています。
「僕の子どもの時代は、毎日暗くなるまで遊んでいました。
もちろん遊びたくって遊んでたんですけど、家にいたって、ろくな事はないんです。
親に用を言いつけられるか、勉強しろって言われるでしょう。
それに、おやつらしいものがあるわけでもない。
僕と同じ境遇の友だちはいっぱいいて、自然に群れになるんです。
だけどいまの子どもは冷蔵庫を開ければおやつはあるし、母はあまり文句は言わないし、
自分の部屋にいれば何をしてもわからないし、テレビもファミコンもあるし、
これでなお外に出て遊ぶなんて、
何でわざわざという感じになるんじゃないかなあ」
いまの子どもたちに、わざわざ外に出て友だちと群れて遊ぶ面白さを、
いっぱい体験させてあげたいなあと思っています。
by あかちゃんせんせい
講座レポート④ 自由に遊べる“雰囲気”をつくりだす!
冒険遊び場では、『なにかやってみたい』ことを
ひとつでも多くできるように、様々な工夫がされています。
一つ目のキーワードは、遊び場の運営は、住民が担う。ということ。
自分たちの遊び場をどうしたいのかを話し合い、自分たちで行動する!
みんなで知恵を出し合ったら、一人ではできないことも、大きな力に・・・
具体的には、
火が使えるように役所や消防署に届けを出したり、
工作が自由にできるように、のこぎりやかなづち、くぎ、廃材を置いたり、
遊びに使えそうなもの(ドラム缶やリアカーなど)をもらってきたり、
口コミで共感の輪(仲間)を広げたり、といろんな方の協力で運営されてます。
二つ目のキーワードは、子どもたちがやりたいことをやれるよう、
遊び心を引き出す役のプレーリーダーと呼ばれる大人の存在があります。
プレーリーダーのらいおんは、『プレーリーダーは遊ばせ屋じゃないよ』
だから、『しなきゃいけない』とか『子どもに何かしてやろう』もないよ。
とすごく自然体でした。
三つ目のキーワードは、遊び場づくりに欠かせない
大人向けへのメッセージを書いた看板を掲示されています。

『教えたくなるけど』でも『見てるだけ』
『それじゃだめ』『やってあげよう』『やめなさい』
と言う前に子どもたちの表情をのぞいてみませんか?
大らかに見守ろうと!
遊びに必要な三間(空間・時間・仲間)が失われてきた原因は、大人にあるのでは?
事故やケガがあった時の責任追及の風潮の強さや大人の価値観で子どもの遊びを制限していることなど、
そんなメッセージを大人に発信することで、遊び場づくりに共感する大人の輪を広げていくことが大切。
ほかにも、冒険遊び場づくりのいろんなコツを伝授してもらいました!
わのたねのぷうさんとなおっちが、写真のようにうまくまとめてくれました。

・自分も楽しもう!何か食べて、何かつくって。遊び場では自分の好きなことをしてるよ。
・道具の補修や準備、後片付けも子どもたちと同じ時間、場所でしてるよ。
・後片付けはさせたりなんかしてないよ。いつも忙しい子どもたちには、最後まで遊びきってほしいという思いから。でも、自然と手伝ってくれたりする子もいるよ。
・工具も遊び道具の一つ。危険度の高いナタなんかは、大怪我しないように刃に気配りしてたり、始めての子どもが多い時には、そっと抜いたりしてるよ。
・ガキ大将なんか最初からいないよ。子ども同士の付き合いの中から自然にリーダーが現れてくるもんよ。年上だから『はい、リーダーね』なんてことは、なしよ。
・子どもとの会話だけでなく、親や近所の方との雑談も楽しいし、大切にしているよ。
・他のスタッフの状況は何となく把握して、行動してるよ。
・子どもとは、その時の状況・バランスで突き放したり、一緒に遊んだりしてるよ。
・冒険遊び場つくりは、子どもから学ぶし、他のプレーパークからも学べるよ!
最後に、あせらずゆっくり雰囲気をつくっていったらいいよと暖かいメッセージをいただきました。
冒険遊び場では、『なにかやってみたい』ことを
ひとつでも多くできるように、様々な工夫がされています。
一つ目のキーワードは、遊び場の運営は、住民が担う。ということ。
自分たちの遊び場をどうしたいのかを話し合い、自分たちで行動する!
みんなで知恵を出し合ったら、一人ではできないことも、大きな力に・・・
具体的には、
火が使えるように役所や消防署に届けを出したり、
工作が自由にできるように、のこぎりやかなづち、くぎ、廃材を置いたり、
遊びに使えそうなもの(ドラム缶やリアカーなど)をもらってきたり、
口コミで共感の輪(仲間)を広げたり、といろんな方の協力で運営されてます。
二つ目のキーワードは、子どもたちがやりたいことをやれるよう、
遊び心を引き出す役のプレーリーダーと呼ばれる大人の存在があります。
プレーリーダーのらいおんは、『プレーリーダーは遊ばせ屋じゃないよ』
だから、『しなきゃいけない』とか『子どもに何かしてやろう』もないよ。
とすごく自然体でした。
三つ目のキーワードは、遊び場づくりに欠かせない
大人向けへのメッセージを書いた看板を掲示されています。

『教えたくなるけど』でも『見てるだけ』
『それじゃだめ』『やってあげよう』『やめなさい』
と言う前に子どもたちの表情をのぞいてみませんか?
大らかに見守ろうと!
遊びに必要な三間(空間・時間・仲間)が失われてきた原因は、大人にあるのでは?
事故やケガがあった時の責任追及の風潮の強さや大人の価値観で子どもの遊びを制限していることなど、
そんなメッセージを大人に発信することで、遊び場づくりに共感する大人の輪を広げていくことが大切。
ほかにも、冒険遊び場づくりのいろんなコツを伝授してもらいました!
わのたねのぷうさんとなおっちが、写真のようにうまくまとめてくれました。

・自分も楽しもう!何か食べて、何かつくって。遊び場では自分の好きなことをしてるよ。
・道具の補修や準備、後片付けも子どもたちと同じ時間、場所でしてるよ。
・後片付けはさせたりなんかしてないよ。いつも忙しい子どもたちには、最後まで遊びきってほしいという思いから。でも、自然と手伝ってくれたりする子もいるよ。
・工具も遊び道具の一つ。危険度の高いナタなんかは、大怪我しないように刃に気配りしてたり、始めての子どもが多い時には、そっと抜いたりしてるよ。
・ガキ大将なんか最初からいないよ。子ども同士の付き合いの中から自然にリーダーが現れてくるもんよ。年上だから『はい、リーダーね』なんてことは、なしよ。
・子どもとの会話だけでなく、親や近所の方との雑談も楽しいし、大切にしているよ。
・他のスタッフの状況は何となく把握して、行動してるよ。
・子どもとは、その時の状況・バランスで突き放したり、一緒に遊んだりしてるよ。
・冒険遊び場つくりは、子どもから学ぶし、他のプレーパークからも学べるよ!
最後に、あせらずゆっくり雰囲気をつくっていったらいいよと暖かいメッセージをいただきました。
まちは遊び場
私たちの子どものころは、まち全体が遊び場だった。
公民館の広場で三角ベースをして遊び、
それに飽きたら宮さん(神社) に行って秘密基地ごっこをし、
それにも飽きたら、よその家の裏庭を通って(近道して)、
友だちの家にあがって、ファミコンをする。
─そんなふうにして遊んでいた。
公民館の前の広場も、宮さんも、田んぼのあぜ道や水路も、友だちの家も、
それら全体が遊べる環境であったし、
遊べる雰囲気が漂っていた。
危険なことやヤンチャなことは、
大人たちに注意されたけれど、
それができないような環境にされてしまうことはなく、
自由に遊べる状態は保たれていた。
そのような環境は、都市化がすすんだ地域ほどなくなってきている。
東近江市はどうだろう。地区によって、いろいろかな?
いま全国各地で盛んになっているプレイパークの活動。
「子どもに自由に遊べる環境を」という趣旨だが、
定期開催では、やはりイベント的に感じるのは否めない。
参加者がお客さんという立場の
一般のイベントとは違う部分がたくさんあるのだけれど、
開催日の活動だけで終わらせてしまったら、
単なるイベントと言われても仕方がない。
私たちは、プレイパークの活動の、その向こうに、
上の述べたような環境を地域に取り戻すという目標を置きたいと思う。
それを目指して、プレイパークの運動にかかわってくださっている方もいる。
プレイパークによって、
子どものおかれている環境や子どもの遊びの大切さを
大人が認識し、
それを広めていくことで、
少しずつでも目標に近づいていきたい。
私たちの子どものころは、まち全体が遊び場だった。
公民館の広場で三角ベースをして遊び、
それに飽きたら宮さん(神社) に行って秘密基地ごっこをし、
それにも飽きたら、よその家の裏庭を通って(近道して)、
友だちの家にあがって、ファミコンをする。
─そんなふうにして遊んでいた。
公民館の前の広場も、宮さんも、田んぼのあぜ道や水路も、友だちの家も、
それら全体が遊べる環境であったし、
遊べる雰囲気が漂っていた。
危険なことやヤンチャなことは、
大人たちに注意されたけれど、
それができないような環境にされてしまうことはなく、
自由に遊べる状態は保たれていた。
そのような環境は、都市化がすすんだ地域ほどなくなってきている。
東近江市はどうだろう。地区によって、いろいろかな?
いま全国各地で盛んになっているプレイパークの活動。
「子どもに自由に遊べる環境を」という趣旨だが、
定期開催では、やはりイベント的に感じるのは否めない。
参加者がお客さんという立場の
一般のイベントとは違う部分がたくさんあるのだけれど、
開催日の活動だけで終わらせてしまったら、
単なるイベントと言われても仕方がない。
私たちは、プレイパークの活動の、その向こうに、
上の述べたような環境を地域に取り戻すという目標を置きたいと思う。
それを目指して、プレイパークの運動にかかわってくださっている方もいる。
プレイパークによって、
子どものおかれている環境や子どもの遊びの大切さを
大人が認識し、
それを広めていくことで、
少しずつでも目標に近づいていきたい。
東近江市中小路町にホルモンがおいしい焼肉屋があります。
その焼肉屋の隣には
現在、賃貸マンションが立っているのですが、
私が子どものころ、そこは土砂置き場でした。
ドーンとそびえる土砂の山は、子どもたち格好の遊び場で、
よく登って遊んだものです。
土砂はすぐに崩れるので、
けっこう気合いを入れないと登れません。
なので、その頂に立ったときは
達成感と爽快さに満たされたのでした。
そういえば、登りやすいようにと、
斜面を削ったり踏み固めたりして階段もつくったっけなぁ。
冬になって雪が降ったら、斜面をそりでシュ~ッと滑る。
そりがなかったら、肥料袋をお尻に敷いてズリズリ~ッと滑る。
懐かしい思い出です。
みなさんにも、そのような思い出があるのではないでしょうか。
『こどものあそび環境』『こどもとあそび』などの著書がある
環境デザイン研究所の仙田満さんは
「子どもたちは工事現場のような、どこか冒険的な空間が好きだ」
と述べています。
仙田さんは工事現場のようなごちゃごちゃとしているスペースや
土砂・建材置き場、廃屋のようなきっちりと管理されていない状態の空間を
「アナーキースペース」と呼び、そういう空間は子どもたちにとって、
「何となくただのもの集積ではなく、想像力をかきたてる遊びと場」
であると語っています。
しかし近年では、アナーキースペースと呼ぶにふさわしい空間は、
きわめて少なくなっています。
ヨーロッパには子どもたちのために、
アナーキースペースを公園化したようなものがあるそうです。
仙田さんは
「アナーキースペースも公園として造らねばならないというのが、現代という時代なのだ」
と嘆かれています。
by あかちゃんせんせい
その焼肉屋の隣には
現在、賃貸マンションが立っているのですが、
私が子どものころ、そこは土砂置き場でした。
ドーンとそびえる土砂の山は、子どもたち格好の遊び場で、
よく登って遊んだものです。
土砂はすぐに崩れるので、
けっこう気合いを入れないと登れません。
なので、その頂に立ったときは
達成感と爽快さに満たされたのでした。
そういえば、登りやすいようにと、
斜面を削ったり踏み固めたりして階段もつくったっけなぁ。
冬になって雪が降ったら、斜面をそりでシュ~ッと滑る。
そりがなかったら、肥料袋をお尻に敷いてズリズリ~ッと滑る。
懐かしい思い出です。
みなさんにも、そのような思い出があるのではないでしょうか。
『こどものあそび環境』『こどもとあそび』などの著書がある
環境デザイン研究所の仙田満さんは
「子どもたちは工事現場のような、どこか冒険的な空間が好きだ」
と述べています。
仙田さんは工事現場のようなごちゃごちゃとしているスペースや
土砂・建材置き場、廃屋のようなきっちりと管理されていない状態の空間を
「アナーキースペース」と呼び、そういう空間は子どもたちにとって、
「何となくただのもの集積ではなく、想像力をかきたてる遊びと場」
であると語っています。
しかし近年では、アナーキースペースと呼ぶにふさわしい空間は、
きわめて少なくなっています。
ヨーロッパには子どもたちのために、
アナーキースペースを公園化したようなものがあるそうです。
仙田さんは
「アナーキースペースも公園として造らねばならないというのが、現代という時代なのだ」
と嘆かれています。
by あかちゃんせんせい