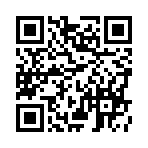3月のプレーパークは
地元の祭のために参加できず、
後片付けにだけ行きました。
あそびまくった跡が
あちらこちらに残っていて、
楽しかった様子が伝わってきました。
ふと見ると
増改築中の地下秘密基地の玄関先に
こんなにかわいい飾り付けがしてあって、
とても感動しました。
子どものセンスって大人にはないものがあるなぁと思いました。
コーチング・クリニック5月号に
「子どもの体力向上について」というテーマの特集があります。
日本冒険遊び場協会の理事の天野秀昭さんが
「“外遊び”と子どもの体力」について語られるそうです。
そして、こうした外遊びができる場所として、
全国の冒険遊び場が紹介され、
我が『八日市冒険遊び場』も載せていただくことになりました。
3月27日に発売予定です。必見です。
この「子どもの体力向上」については、
子ども達と毎週バドミントンをしている
ぶらいあんはとても興味を持っています。
みなさん、『スキャモンの発達曲線』って、ご存知ですか?
詳しくは、いろんな方が解説されているので調べてみてほしいのですが、
要は、からだの発達の特性で、
子ども時代にはすごく運動神経が発達しやすいということをいっています。
(プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジとも言われるくらい大切な時期なんです!)
例えば、自転車とか一輪車。
子どもは、しばらく練習するといつの間にか乗れるようになりますよね。
そして、大人になって久しぶりに乗っても乗れる。
でも、大人になってから、初めて自転車や一輪車に乗ろうとしたら、これは大変。
子ども時代は、即座の習得といって、何をやってもすぐできてしまう年齢なんです。
(個人差はありますが・・・)
このことが、からだの動きについて全て言えることで、
スポーツでも何でも一番必要なのは、
歩く、走る、投げる、跳ぶ─といったからだのバランス。
そして、このからだのバランスをつくるのに必要なのが、“遊び”だと思っています。
私が冒険遊び場を始めたひとつに、
外で走り回ったり、木に登ったり、跳んだり、ドラム缶に乗ったり・・・
こうしたからだを使って思いっきり遊んで、
からだが丈夫で健康な子どもたちに育って欲しいという思いを持っていたからです。
なにせ、一番成長しやすい子ども時期に、
からだを動かさないのは、もったいないですからね。
「子どもの体力向上について」というテーマの特集があります。
日本冒険遊び場協会の理事の天野秀昭さんが
「“外遊び”と子どもの体力」について語られるそうです。
そして、こうした外遊びができる場所として、
全国の冒険遊び場が紹介され、
我が『八日市冒険遊び場』も載せていただくことになりました。

3月27日に発売予定です。必見です。
この「子どもの体力向上」については、
子ども達と毎週バドミントンをしている
ぶらいあんはとても興味を持っています。
みなさん、『スキャモンの発達曲線』って、ご存知ですか?
詳しくは、いろんな方が解説されているので調べてみてほしいのですが、
要は、からだの発達の特性で、
子ども時代にはすごく運動神経が発達しやすいということをいっています。
(プレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジとも言われるくらい大切な時期なんです!)
例えば、自転車とか一輪車。
子どもは、しばらく練習するといつの間にか乗れるようになりますよね。
そして、大人になって久しぶりに乗っても乗れる。
でも、大人になってから、初めて自転車や一輪車に乗ろうとしたら、これは大変。
子ども時代は、即座の習得といって、何をやってもすぐできてしまう年齢なんです。
(個人差はありますが・・・)
このことが、からだの動きについて全て言えることで、
スポーツでも何でも一番必要なのは、
歩く、走る、投げる、跳ぶ─といったからだのバランス。
そして、このからだのバランスをつくるのに必要なのが、“遊び”だと思っています。
私が冒険遊び場を始めたひとつに、
外で走り回ったり、木に登ったり、跳んだり、ドラム缶に乗ったり・・・
こうしたからだを使って思いっきり遊んで、
からだが丈夫で健康な子どもたちに育って欲しいという思いを持っていたからです。
なにせ、一番成長しやすい子ども時期に、
からだを動かさないのは、もったいないですからね。
食品運搬用の穴のあいたばんじゅうを乗せて
そこに雪の塊を入れます。
雪の塊が砕けて
穴からサラサラの雪が
下に落ちます。
一升瓶のケースに
サラサラの雪がたまっています。
これを集めて・・・
さあ、召し上がれ

 スーパーの床の模様や、
スーパーの床の模様や、駅のタイルの線に沿って
ウネウネ歩く子ども。
年末、お店は混み合っているのに、
ウネウネ歩かれると、
「ちょっとまっすぐ歩いてよ
 」
」と言ってしまいますが、
自分も子どものころ
そういうことするの好きだったな・・・。
(この「ウネウネ」を
公園づくりに活かせないかな・・・と思った次第です。)
白い台と白い台の間をつかって、
“エアーホッケー”です。
全然エアーは出てないのですが・・・。
出ているとしたら、子どもの荒い息だけです。
ゴルフボールを打ち合って、
相手が打ち返せなかったり、
ボールが相手の体に触れたりしたら
得点できます。
小さい頃家の廊下で、こんな遊びをした覚えありませんか?
私は今でもやっています(娘と対戦)。
雨で外で遊べないとき、廊下が遊び場になります。
あかちゃんせんせい
こどもの体力は遊びから という社説が
体育の日の朝日新聞に掲載されてました。

暗くなるまで外で思いっきり遊ぶ・・・
体力がつくのはよくわかるなあ。
そして、いっぱい食べて、いっぱい寝る。
そんな当たり前の子ども時代を
我が子たちにもさせてあげたい・・・
体育の日の朝日新聞に掲載されてました。

暗くなるまで外で思いっきり遊ぶ・・・
体力がつくのはよくわかるなあ。
そして、いっぱい食べて、いっぱい寝る。
そんな当たり前の子ども時代を
我が子たちにもさせてあげたい・・・
3年前、保育園の4歳児を担任していた頃、
「龍」をテーマに冒険をしたり、お話を作ったりしながら保育を展開していました。
*********************************************
夏に子どもたちと“虹色の龍”を作って部屋に飾りました。
その龍に、山を探検して手に入れた
「いのちの水」(湧き水)を飲ませると、
夕方、子どもたちが帰ったあと、
龍が動き出して保育園から出て行ったのです。
次の日、龍に“いのち”が宿って
飛んでいった話を、子どもたちに写真を見せながら話しました。
その龍は天を飛んでいる途中、
流星にぶつかってケガをし、
保育園に戻ってきて、力尽きました。
そして、いまに至るまで廊下の天井に飾ってあります。 動き出した“龍”
 うちの保育園は学童保育もしているのですが、
うちの保育園は学童保育もしているのですが、
今日、小学2年生になった当時の教え子たちが、
その龍を見上げて、 小学1年生の子どもたちに
「この龍、生きとったんやで」 と一生懸命に説明していました。
1年生たちは
「え~っ、そんなんうそやで」と言っていましたが、
2年生たちは真剣そのものに
「いのちの水を飲ましたら、生きよってんで」
と語っているのでした。
外へと飛んでいく“龍”
*********************************************
私はこういう子どもを育てたいんです。
子どもにしか見えない世界をいっぱい体験させてやりたいんです。
今日の2年生たちの姿は本当にうれしかったです。
「龍」をテーマに冒険をしたり、お話を作ったりしながら保育を展開していました。
*********************************************
夏に子どもたちと“虹色の龍”を作って部屋に飾りました。
その龍に、山を探検して手に入れた

「いのちの水」(湧き水)を飲ませると、
夕方、子どもたちが帰ったあと、
龍が動き出して保育園から出て行ったのです。
次の日、龍に“いのち”が宿って
飛んでいった話を、子どもたちに写真を見せながら話しました。
その龍は天を飛んでいる途中、
流星にぶつかってケガをし、
保育園に戻ってきて、力尽きました。
そして、いまに至るまで廊下の天井に飾ってあります。 動き出した“龍”
 うちの保育園は学童保育もしているのですが、
うちの保育園は学童保育もしているのですが、今日、小学2年生になった当時の教え子たちが、
その龍を見上げて、 小学1年生の子どもたちに
「この龍、生きとったんやで」 と一生懸命に説明していました。
1年生たちは
「え~っ、そんなんうそやで」と言っていましたが、
2年生たちは真剣そのものに
「いのちの水を飲ましたら、生きよってんで」
と語っているのでした。
外へと飛んでいく“龍”
*********************************************
私はこういう子どもを育てたいんです。
子どもにしか見えない世界をいっぱい体験させてやりたいんです。
今日の2年生たちの姿は本当にうれしかったです。
あかちゃんせんせい
以前のコメントから紹介します。
子どもの頃の遊びの武勇伝です。
*********************************************
ジョゼフさんの武勇伝
落ちてるウンコに爆竹さして、破裂する前に
飛び掛らない場所まで ダッシュ!ε≡≡ヘ( ´∀`)ノ
弟と一緒に遊んでたから、小さな弟は逃げおくれ、
全身ウンコまみれ!
異常に笑えたww
ん?武勇伝ではないかもww
アンコさんの武勇伝
友だちと宮さんにあそびに行って、
「うわっ、お金見つけたで!」
と、“宝探し”の感覚でお賽銭を頂戴しました。
罪の意識などはまったくなく、
「何でここにお金があるんやろう?」
と思いつつ、財宝を掘り当てたようなうれしさいっぱいで
友だちと山分け

ちなみにもう時効です(たぶん)
あかちゃんせんせいの武勇伝
小学校高学年の頃は、私たち悪ガキたちが集まって、
隣在所の神社の林に秘密基地を造営しました。
大人たちが基地を壊しに近づけないように、
さまざまなトラップを仕掛けました。
子どもの背丈で腰まで埋まるくらいの落とし穴。
あやまって自分たちがはまってしまいました。
木と木の間にピンッと張られた釣り糸に触れると、
頭上から槍がズドン・・・ という
という
危険極まりないトラップもつくりました。
ひかかったら軽傷ではすまなかっただろうなぁ。
太い丈夫な木の上には、床を張って見張り台をこしらえ、
そこから、敵(大人)を狙撃 することができました。
することができました。
あれは一応、秘密基地ごっこだったのだが、
あれこれ工夫しながら基地をつくる工程がおもしろかったように思います。
*********************************************
かわいらしい武勇伝をお持ちの方、
または凄まじい武勇伝をお持ちの方、
その伝説を教えてください。
子どもの頃の遊びの武勇伝です。
*********************************************
ジョゼフさんの武勇伝
落ちてるウンコに爆竹さして、破裂する前に
飛び掛らない場所まで ダッシュ!ε≡≡ヘ( ´∀`)ノ
弟と一緒に遊んでたから、小さな弟は逃げおくれ、
全身ウンコまみれ!
異常に笑えたww
ん?武勇伝ではないかもww
アンコさんの武勇伝
友だちと宮さんにあそびに行って、
「うわっ、お金見つけたで!」
と、“宝探し”の感覚でお賽銭を頂戴しました。
罪の意識などはまったくなく、
「何でここにお金があるんやろう?」
と思いつつ、財宝を掘り当てたようなうれしさいっぱいで
友だちと山分け

ちなみにもう時効です(たぶん)

あかちゃんせんせいの武勇伝
小学校高学年の頃は、私たち悪ガキたちが集まって、
隣在所の神社の林に秘密基地を造営しました。
大人たちが基地を壊しに近づけないように、
さまざまなトラップを仕掛けました。
子どもの背丈で腰まで埋まるくらいの落とし穴。
あやまって自分たちがはまってしまいました。
木と木の間にピンッと張られた釣り糸に触れると、
頭上から槍がズドン・・・
 という
という危険極まりないトラップもつくりました。
ひかかったら軽傷ではすまなかっただろうなぁ。
太い丈夫な木の上には、床を張って見張り台をこしらえ、
そこから、敵(大人)を狙撃
 することができました。
することができました。あれは一応、秘密基地ごっこだったのだが、
あれこれ工夫しながら基地をつくる工程がおもしろかったように思います。
*********************************************
かわいらしい武勇伝をお持ちの方、
または凄まじい武勇伝をお持ちの方、
その伝説を教えてください。
河辺いきものの森で
竹退治と薪割りに汗を流してきました。
楽しみはお昼ご飯。
この地で採れた
旬のものを使った料理は、
素朴だけれど
本当のご馳走です。
作業をしながら、
「まるで、きのこのマンションや~」
と叫びたくなるくらい
きのこに覆われた大木や、
陸生の蛍、
そして網を手に虫つかみをする小学生たちなど、
なかなかお目にかかれないものを目にしました。
「まるで、きのこのマンションや~」
と叫びたくなるくらい
きのこに覆われた大木や、
陸生の蛍、
そして網を手に虫つかみをする小学生たちなど、
なかなかお目にかかれないものを目にしました。
川でザリガニをとったりして
ネイチャーセンターに戻ってきたとき、
パッ!と
目の前をタマムシが飛んでいきました。
小学生たちのテンション
 あがるあがる
あがるあがる
高い空を飛ぶタマムシを追いかけまわし、
大木のてっぺんにとまったタマムシを
木によじ登ってつかまえようとする・・・(結局とれませんでした)。
見ていると、
とても懐かしい気分になりました。
「テレビゲームより外で遊ぶ方がいい?」
と、バカな質問をすると、
「外で遊んでる方が、めっちゃおもしろいな」
「うん。前はゲームやってたんやけど、
あたま痛くなってもうやめてん。」
と少年たち。

「見てみ。これぼくの
宝物やねん」
と、タマムシみたいに
きれいに光る虫を
見せてくれました。
とても懐かしい気分になりました。
「テレビゲームより外で遊ぶ方がいい?」
と、バカな質問をすると、
「外で遊んでる方が、めっちゃおもしろいな」
「うん。前はゲームやってたんやけど、
あたま痛くなってもうやめてん。」
と少年たち。
「見てみ。これぼくの
宝物やねん」
と、タマムシみたいに
きれいに光る虫を
見せてくれました。
子どもたちが目を輝かして遊べる環境、
みんなで考えて生きたいですね。
みんなで考えて生きたいですね。
by あかちゃんせんせい
原風景
子どものころの遊びを思い返してみると、
自分たちが遊んでいた風景も思い出されて、懐かしい気分になる。
それは、心の中にあって忘れることのできない、
我々がふと立ち返ることのできる風景。
映像的に心に焼きついて記憶されている、幼い日を過ごした場所・環境。
つまり「ふるさと」。
そういうものを「原風景」と呼ぶのだろう。
誰もが思い当たる原風景というものがあるだろう。
幼いころ、駆けずり回って遊んだ野原や神社、
友だちと遊んだ校庭、
釣りをした溜池、
夢中になった昆虫採集─
「原体験」という言葉がある。
その人の人格を形成するのに影響した、通常、幼い日の体験をそう言うが、
原風景とともに思い起こされる遊びは、
まさに原体験と呼べるのではないか。
心と体の奥深くに記憶された幼いときの豊かな原風景・原体験は,
創造性,人間性豊かに育つための基盤となるだろう。
また、ふるさとに愛着を持っている人は、豊かな原風景を持っている。
そんな原風景・原体験を
子どもたちに大切に心に刻んでいってほしい。
いまの遊びと昔の遊びについて、
以前、大先輩の男性保育者と話をしたことがあります。
おもちゃに関しては、圧倒的に現在の子どもの方が充実しています。
祖父母、それから父母世代が子どもだった頃は、おもちゃはそれほどなく、
自分たちでつくり、自分たちで遊びを考えていました。
祖父母-父母世代の遊びは、1人ではできないものや、
1人でするよりも友だちと数人でした方が楽しいものが多いようです。
これに対して現在の子どもの遊びは、
1人でも遊べるものがたくさんあります。また、
「主な遊びを見てみると、おもちゃがそんなになかった時代は、
何にもないところから遊びが出発しているけれど、
いまの子どもの遊びは、あるところから出発している」
と、その保育者は話していました。
“何にもない”ところからの出発は、
経験や知恵、想像力、ときには冒険心が必要になることもあります。
異年齢の子どもたちで遊ぶことが多かった時代、
年長者の経験と知恵は、その遊びをより楽しくしたでしょう。
テレビゲームに代表される「ある」ところから出発する遊びは、
遊びの内容がしっかり決められていて、
発想が入り込むあまりないのかなぁ(テレビゲームのことはあまり知らないけれど・・・)。
by あかちゃんせんせい
以前、大先輩の男性保育者と話をしたことがあります。
おもちゃに関しては、圧倒的に現在の子どもの方が充実しています。
祖父母、それから父母世代が子どもだった頃は、おもちゃはそれほどなく、
自分たちでつくり、自分たちで遊びを考えていました。
祖父母-父母世代の遊びは、1人ではできないものや、
1人でするよりも友だちと数人でした方が楽しいものが多いようです。
これに対して現在の子どもの遊びは、
1人でも遊べるものがたくさんあります。また、
「主な遊びを見てみると、おもちゃがそんなになかった時代は、
何にもないところから遊びが出発しているけれど、
いまの子どもの遊びは、あるところから出発している」
と、その保育者は話していました。
“何にもない”ところからの出発は、
経験や知恵、想像力、ときには冒険心が必要になることもあります。
異年齢の子どもたちで遊ぶことが多かった時代、
年長者の経験と知恵は、その遊びをより楽しくしたでしょう。
テレビゲームに代表される「ある」ところから出発する遊びは、
遊びの内容がしっかり決められていて、
発想が入り込むあまりないのかなぁ(テレビゲームのことはあまり知らないけれど・・・)。
by あかちゃんせんせい
佐々木正美さんの著書の中に
「三間(サンマ)があっても遊べない子どもたち」という記事を見つけました。
東京・大田区にある児童館の指導員さんの投稿に、
「時間を与えて、空間を与えて、仲間を与えてみたけれど、
そんなことで現代っ子は遊べなかった」
とあり、
「一定の指導やサポートも必要である」
と書かれていたそうです。
わかります。
遊びを知らないと、遊べませんものね。
佐々木さんは、いまの子どもの遊べない理由を
「想像力・創造力の未熟さ」においておられます。
そして、「想像力・創造力は遊びの中で発達する」
とも述べられています。
上記の遊べない子どもたちも、
「一定のサポート」を受けて毎日遊ぶ中で、
想像力・創造力をはぐくみ、
遊べるようになっていくのでしょうね。
どうせなら「一定のサポート」をするのが、
年上の子どもであるような社会にしたいですね。
それにしても、
「想像力が発達しないと、他者の気持ちを想像する力が育たない」
といいますから、
本当に遊びは大切なのだと思います。
by あかちゃんせんせい
「三間(サンマ)があっても遊べない子どもたち」という記事を見つけました。
東京・大田区にある児童館の指導員さんの投稿に、
「時間を与えて、空間を与えて、仲間を与えてみたけれど、
そんなことで現代っ子は遊べなかった」
とあり、
「一定の指導やサポートも必要である」
と書かれていたそうです。
わかります。
遊びを知らないと、遊べませんものね。
佐々木さんは、いまの子どもの遊べない理由を
「想像力・創造力の未熟さ」においておられます。
そして、「想像力・創造力は遊びの中で発達する」
とも述べられています。
上記の遊べない子どもたちも、
「一定のサポート」を受けて毎日遊ぶ中で、
想像力・創造力をはぐくみ、
遊べるようになっていくのでしょうね。
どうせなら「一定のサポート」をするのが、
年上の子どもであるような社会にしたいですね。
それにしても、
「想像力が発達しないと、他者の気持ちを想像する力が育たない」
といいますから、
本当に遊びは大切なのだと思います。
by あかちゃんせんせい
東近江市中小路町にホルモンがおいしい焼肉屋があります。
その焼肉屋の隣には
現在、賃貸マンションが立っているのですが、
私が子どものころ、そこは土砂置き場でした。
ドーンとそびえる土砂の山は、子どもたち格好の遊び場で、
よく登って遊んだものです。
土砂はすぐに崩れるので、
けっこう気合いを入れないと登れません。
なので、その頂に立ったときは
達成感と爽快さに満たされたのでした。
そういえば、登りやすいようにと、
斜面を削ったり踏み固めたりして階段もつくったっけなぁ。
冬になって雪が降ったら、斜面をそりでシュ~ッと滑る。
そりがなかったら、肥料袋をお尻に敷いてズリズリ~ッと滑る。
懐かしい思い出です。
みなさんにも、そのような思い出があるのではないでしょうか。
『こどものあそび環境』『こどもとあそび』などの著書がある
環境デザイン研究所の仙田満さんは
「子どもたちは工事現場のような、どこか冒険的な空間が好きだ」
と述べています。
仙田さんは工事現場のようなごちゃごちゃとしているスペースや
土砂・建材置き場、廃屋のようなきっちりと管理されていない状態の空間を
「アナーキースペース」と呼び、そういう空間は子どもたちにとって、
「何となくただのもの集積ではなく、想像力をかきたてる遊びと場」
であると語っています。
しかし近年では、アナーキースペースと呼ぶにふさわしい空間は、
きわめて少なくなっています。
ヨーロッパには子どもたちのために、
アナーキースペースを公園化したようなものがあるそうです。
仙田さんは
「アナーキースペースも公園として造らねばならないというのが、現代という時代なのだ」
と嘆かれています。
by あかちゃんせんせい
その焼肉屋の隣には
現在、賃貸マンションが立っているのですが、
私が子どものころ、そこは土砂置き場でした。
ドーンとそびえる土砂の山は、子どもたち格好の遊び場で、
よく登って遊んだものです。
土砂はすぐに崩れるので、
けっこう気合いを入れないと登れません。
なので、その頂に立ったときは
達成感と爽快さに満たされたのでした。
そういえば、登りやすいようにと、
斜面を削ったり踏み固めたりして階段もつくったっけなぁ。
冬になって雪が降ったら、斜面をそりでシュ~ッと滑る。
そりがなかったら、肥料袋をお尻に敷いてズリズリ~ッと滑る。
懐かしい思い出です。
みなさんにも、そのような思い出があるのではないでしょうか。
『こどものあそび環境』『こどもとあそび』などの著書がある
環境デザイン研究所の仙田満さんは
「子どもたちは工事現場のような、どこか冒険的な空間が好きだ」
と述べています。
仙田さんは工事現場のようなごちゃごちゃとしているスペースや
土砂・建材置き場、廃屋のようなきっちりと管理されていない状態の空間を
「アナーキースペース」と呼び、そういう空間は子どもたちにとって、
「何となくただのもの集積ではなく、想像力をかきたてる遊びと場」
であると語っています。
しかし近年では、アナーキースペースと呼ぶにふさわしい空間は、
きわめて少なくなっています。
ヨーロッパには子どもたちのために、
アナーキースペースを公園化したようなものがあるそうです。
仙田さんは
「アナーキースペースも公園として造らねばならないというのが、現代という時代なのだ」
と嘆かれています。
by あかちゃんせんせい
「子どもが外で遊べない、遊ばない」、「子どもの外遊びが減っている」
と言われる問題について、
「三間(空間・時間・仲間)がない」ということがよく言われています。
子どもが遊べる場所が減ってきたり、
塾やお稽古で遊ぶ時間がなかったり、
近所に子どもが少なかったりということですね。
先日の「冒険遊び場作りきっかけ講座」の分団協議の中では、
親が子どもの遊びを制限してしまっているのではないか,
という指摘がありました。
危ないことや汚いことはさせなかったり、
事なかれ主義で子ども同士のやり取りをリードしていたりして、
子どもの遊びは管理されている状態であること、
親同士のつながりがないために,子ども同士を遊ばせにくかったりすることです。
それらのように、外で遊ぶことを制限する要因があるのと同時に、
子どもを室内遊びにひきつけるものがあるのでしょう。
たとえば、テレビゲームや携帯ゲーム。
私の子ども時代は外でハチャメチャに遊ぶことが多かったけれど、
外ばかりで遊んでたというわけではなく、
友だちの家にあがってファミコンもよくしていました。
それはそれで、やっぱり面白かったです。
子どもの遊びの中心がテレビゲームや携帯ゲームになるのも、わからなくもないです。
外遊びが減り、圧倒的に室内遊びが増えたということについて、
子どもについての評論を多数書かれている斎藤次郎さんは、
次のように言っています。
「僕の子どもの時代は、毎日暗くなるまで遊んでいました。
もちろん遊びたくって遊んでたんですけど、家にいたって、ろくな事はないんです。
親に用を言いつけられるか、勉強しろって言われるでしょう。
それに、おやつらしいものがあるわけでもない。
僕と同じ境遇の友だちはいっぱいいて、自然に群れになるんです。
だけどいまの子どもは冷蔵庫を開ければおやつはあるし、母はあまり文句は言わないし、
自分の部屋にいれば何をしてもわからないし、テレビもファミコンもあるし、
これでなお外に出て遊ぶなんて、
何でわざわざという感じになるんじゃないかなあ」
いまの子どもたちに、わざわざ外に出て友だちと群れて遊ぶ面白さを、
いっぱい体験させてあげたいなあと思っています。
by あかちゃんせんせい
と言われる問題について、
「三間(空間・時間・仲間)がない」ということがよく言われています。
子どもが遊べる場所が減ってきたり、
塾やお稽古で遊ぶ時間がなかったり、
近所に子どもが少なかったりということですね。
先日の「冒険遊び場作りきっかけ講座」の分団協議の中では、
親が子どもの遊びを制限してしまっているのではないか,
という指摘がありました。
危ないことや汚いことはさせなかったり、
事なかれ主義で子ども同士のやり取りをリードしていたりして、
子どもの遊びは管理されている状態であること、
親同士のつながりがないために,子ども同士を遊ばせにくかったりすることです。
それらのように、外で遊ぶことを制限する要因があるのと同時に、
子どもを室内遊びにひきつけるものがあるのでしょう。
たとえば、テレビゲームや携帯ゲーム。
私の子ども時代は外でハチャメチャに遊ぶことが多かったけれど、
外ばかりで遊んでたというわけではなく、
友だちの家にあがってファミコンもよくしていました。
それはそれで、やっぱり面白かったです。
子どもの遊びの中心がテレビゲームや携帯ゲームになるのも、わからなくもないです。
外遊びが減り、圧倒的に室内遊びが増えたということについて、
子どもについての評論を多数書かれている斎藤次郎さんは、
次のように言っています。
「僕の子どもの時代は、毎日暗くなるまで遊んでいました。
もちろん遊びたくって遊んでたんですけど、家にいたって、ろくな事はないんです。
親に用を言いつけられるか、勉強しろって言われるでしょう。
それに、おやつらしいものがあるわけでもない。
僕と同じ境遇の友だちはいっぱいいて、自然に群れになるんです。
だけどいまの子どもは冷蔵庫を開ければおやつはあるし、母はあまり文句は言わないし、
自分の部屋にいれば何をしてもわからないし、テレビもファミコンもあるし、
これでなお外に出て遊ぶなんて、
何でわざわざという感じになるんじゃないかなあ」
いまの子どもたちに、わざわざ外に出て友だちと群れて遊ぶ面白さを、
いっぱい体験させてあげたいなあと思っています。
by あかちゃんせんせい
(静岡県富士市のたごっこパークを視察より)
写真の子どもたちは玄米を使って料理をしています。
これも遊び。調理の指導はありません。
そのときの子どもの思いつきで、味が決まります。
煎って食べたり、煮たり、炊いたり・・・。
煎った玄米も香ばしくておいしかったのですが、
写真の男の子は、砂糖と少量の水を加えて煮詰めていました。
すると、見事な「玄米おこし」の出来上がり!
男の子は出来上がったおこしを、大事そうに、少しずつかじっていました。
右の女の子は炊いた玄米が硬かったので、
水を加えておかゆにしてみました。
でも、どうせなら「リゾットみたいにしよ~」と、コーヒー用の粉末ミルクを加え、
さらにスナック菓子のカールを投入。
カールを入れたことで旨味が加わって、なかなかおいしかったのでした。
そのように、自分の持っているセンスと技術を駆使して、
自分なりのつくり方で何かをつくる。
そして、それに没頭する。
ときには、「こりゃ失敗だな」と思うときや、
想定外のものが出来上がってしまうこともあるのでしょう。
またそれも魅力だなと感じました。
by あかちゃんせんせい
先日、滋賀県が主催する子育て支援セミナーに行ってきました。
テーマは、「地域で支える子育て」
そのパネラーに彦根のプレーパークの会の報告がありました。
【報告内容】
子どもは、本来「危ない、汚い、うるさい」の3拍子そろった、大人から見るとハラハラするもの。
でもそのなかで「工夫してやり遂げる」「試してみて失敗する」
「仲間とワイワイと」「一人でじっくりと」
「小さなけがを繰り返しながら本能的に身を守る」
というような、豊かな体験がある。
子どもたちがこれから
「人」として生きていくうえで必要な「力」を生み出していくのでは。
ところが、近頃の子どもたちは、
遊びの時間・空間・仲間を失いつつあります。
そして、少しのけがや事故でも、
すぐ他人の責任を追及する風潮があります。
こんな大人の態度が、
子どもたちの生活の体験をすごく狭くしているのではないかな?
だから子どもたちには、自由な時間と自由な空間の中で、
自分の責任でとことん「遊びきる」体験をしてほしい!!
ほんと共感しました。
プレーパークの面白さと重要性が伝わってきました。
自分だけ思っていてもなかなかできないけれど、
何人かが思いを共有し集まれば、
子どもの成長と同じように行ったり戻ったりしながら、
前に進むんじゃないかなと思っています。
そんな意味で、こうした環境を地域で作る。
地域で子育てすることの重要性をあらためて感じました。
そして、子どもたちの笑顔のスライドをみて、ほんと”遊び”って大切だと思いました。
by ブライアン
テーマは、「地域で支える子育て」
そのパネラーに彦根のプレーパークの会の報告がありました。
【報告内容】
子どもは、本来「危ない、汚い、うるさい」の3拍子そろった、大人から見るとハラハラするもの。
でもそのなかで「工夫してやり遂げる」「試してみて失敗する」
「仲間とワイワイと」「一人でじっくりと」
「小さなけがを繰り返しながら本能的に身を守る」
というような、豊かな体験がある。
子どもたちがこれから
「人」として生きていくうえで必要な「力」を生み出していくのでは。
ところが、近頃の子どもたちは、
遊びの時間・空間・仲間を失いつつあります。
そして、少しのけがや事故でも、
すぐ他人の責任を追及する風潮があります。
こんな大人の態度が、
子どもたちの生活の体験をすごく狭くしているのではないかな?
だから子どもたちには、自由な時間と自由な空間の中で、
自分の責任でとことん「遊びきる」体験をしてほしい!!
ほんと共感しました。
プレーパークの面白さと重要性が伝わってきました。
自分だけ思っていてもなかなかできないけれど、
何人かが思いを共有し集まれば、
子どもの成長と同じように行ったり戻ったりしながら、
前に進むんじゃないかなと思っています。
そんな意味で、こうした環境を地域で作る。
地域で子育てすることの重要性をあらためて感じました。
そして、子どもたちの笑顔のスライドをみて、ほんと”遊び”って大切だと思いました。
by ブライアン