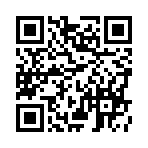2008年12月10日 竹とんぼ教室と竹とんぼ遊びの違い
遊育講演会の報告シリーズ、
第10回は「竹とんぼ教室と竹とんぼ遊びの違い」です。
Q3.
大人がどこまで、子どもに遊びを教えたらいいのか。
昔からの伝承遊びとか、竹とんぼづくりとか、
私達は、昔、先輩に教えて貰って、見よう見まねで作った気がするが
最近よく聞くのが、道具と材料を与えて、自由にさせてあげればとも聞くが、
どのようにしたらいいか教えて下さい。
A3.
僕も、今日は竹とんぼを流行らせたいなと思うときがある。
そのときは、目立つところで、竹とんぼを作っている。
そうすると、何作ってるのと子どもが来る。
そうすると、竹とんぼをつくってるんだけど、というと私も作りたいとなり、
その日のブームになるときがあるが、誰も声をかけてくれないときもある。
これは、あたるもはっけ。あたらぬもはっけ。
子どもがやりたいと思わないとその子の遊びにならない。
そこが、難しいところで、大人が竹とんぼをつくるということを教えるということになると、
竹とんぼ教室になっちゃう。
一度、こんなことがありました。
竹とんぼづくりを仕掛けようと作っていました。
すると、2mくらい離れたところで、子どもが見よう見まねでつくっている。
こちらも声かけずにみていた。
そしたら、やけに気前よくつくっているんです。
つくった人はわかると思いますが、ガシガシ削っているんです。
大丈夫かなとみていたら、案の定、幅がせまくなり、
本人もしまっと思った様子、でも、見ていたら、
本人はボソッと、「まあいいか、おでんの串にしよう」。といった。
こいつは面白いと思い、にじりよっていった。
次も、また、削りすぎて、次は、爪楊枝にしようと持って帰った。
遊びはこれなんですよ。
大人は目的を先に定めるので、竹とんぼが出来ないと失敗したねとなる。
竹とんぼ教室からは、おでんのくしは生まれない。
だけど、遊びは、結末でも、結果でもなく、プロセスそのものなんです。
だから、落とし穴掘ろうぜと掘り出すが、
途中、土器のかけらが出てきたりすると、
最初落とし穴をつくろうぜと集まった仲間は、発掘遊びに変わる。
落とし穴を作ることが遊びではない。
大人はそういうことをわきまえていれば、子どもと遊べる。
大人が結末を決めて、遊んでしまうと、ちょっと違ってくる。
大人主役の〇〇教室になる。
子どもが教えてとくると、どんどん教えればいいと思うが、
誰も教えてくれと言いにこない場合もある。
でも、大人が楽しそうに何かを楽しそうにやっていれば、
子どもにとっては子どもに刺激です。
大人がいばっている顔ばかり見せているとか、
つかれている姿しか見せていないと、
大人自信がいきいきと何かをやっている姿を見ていないです。現代は。
昔は、生活が身近にあったので、大人の様々な姿をマジかに見ることが出来たが、
大人の姿を子どもは見れていない。
大人がすごく楽しそうなことをしている姿そのものは魅力的。
大人がいきいき遊べばいいんだと思えばいいと思いますよ。
以上、10回に分けて報告した講演会の内容は終了です。読破ありがとうございました。
第10回は「竹とんぼ教室と竹とんぼ遊びの違い」です。
Q3.
大人がどこまで、子どもに遊びを教えたらいいのか。
昔からの伝承遊びとか、竹とんぼづくりとか、
私達は、昔、先輩に教えて貰って、見よう見まねで作った気がするが
最近よく聞くのが、道具と材料を与えて、自由にさせてあげればとも聞くが、
どのようにしたらいいか教えて下さい。
A3.
僕も、今日は竹とんぼを流行らせたいなと思うときがある。
そのときは、目立つところで、竹とんぼを作っている。
そうすると、何作ってるのと子どもが来る。
そうすると、竹とんぼをつくってるんだけど、というと私も作りたいとなり、
その日のブームになるときがあるが、誰も声をかけてくれないときもある。
これは、あたるもはっけ。あたらぬもはっけ。
子どもがやりたいと思わないとその子の遊びにならない。
そこが、難しいところで、大人が竹とんぼをつくるということを教えるということになると、
竹とんぼ教室になっちゃう。
一度、こんなことがありました。
竹とんぼづくりを仕掛けようと作っていました。
すると、2mくらい離れたところで、子どもが見よう見まねでつくっている。
こちらも声かけずにみていた。
そしたら、やけに気前よくつくっているんです。
つくった人はわかると思いますが、ガシガシ削っているんです。
大丈夫かなとみていたら、案の定、幅がせまくなり、
本人もしまっと思った様子、でも、見ていたら、
本人はボソッと、「まあいいか、おでんの串にしよう」。といった。
こいつは面白いと思い、にじりよっていった。
次も、また、削りすぎて、次は、爪楊枝にしようと持って帰った。
遊びはこれなんですよ。
大人は目的を先に定めるので、竹とんぼが出来ないと失敗したねとなる。
竹とんぼ教室からは、おでんのくしは生まれない。
だけど、遊びは、結末でも、結果でもなく、プロセスそのものなんです。
だから、落とし穴掘ろうぜと掘り出すが、
途中、土器のかけらが出てきたりすると、
最初落とし穴をつくろうぜと集まった仲間は、発掘遊びに変わる。
落とし穴を作ることが遊びではない。
大人はそういうことをわきまえていれば、子どもと遊べる。
大人が結末を決めて、遊んでしまうと、ちょっと違ってくる。
大人主役の〇〇教室になる。
子どもが教えてとくると、どんどん教えればいいと思うが、
誰も教えてくれと言いにこない場合もある。
でも、大人が楽しそうに何かを楽しそうにやっていれば、
子どもにとっては子どもに刺激です。
大人がいばっている顔ばかり見せているとか、
つかれている姿しか見せていないと、
大人自信がいきいきと何かをやっている姿を見ていないです。現代は。
昔は、生活が身近にあったので、大人の様々な姿をマジかに見ることが出来たが、
大人の姿を子どもは見れていない。
大人がすごく楽しそうなことをしている姿そのものは魅力的。
大人がいきいき遊べばいいんだと思えばいいと思いますよ。
以上、10回に分けて報告した講演会の内容は終了です。読破ありがとうございました。
Posted by
八日市に冒険遊び場を作る会
at
23:11
│Comments(
0
) │
遊育講演会 報告