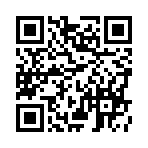2008年12月01日 指導者ではなく、遊び心を誘い出す
10回シリーズでたっぷりお伝えしている、天野さんの講演の内容
第4回目は、「指導者ではなく、遊び心を誘い出す」です。
冒険遊び場・講演会 「遊びは生きる力だ!」より、
意地悪というのは子どもの遊びにはつき物。ちょっとした意地悪はつきもの。いじめという言葉は、意地悪の境目は難しいかもしれない。で、子どもの同士の間では意地悪は普通に起こるが、力関係を噴出し起こりうる。
意地悪の範囲は、やはり、子どもの中にあっては、それも仕方のない関係、必要とまで言いがたいが、仕方のない関係。それは、現実として受け入れないと行かない関係。そこのところに大人がしゃしゃりでてはいけないと思うが、これは、いじめであると思うものは。例えば、僕自身が判断するのは、片方が抵抗する気力がない、感じがない、一方的にやり続けている場合、人数的に、力関係で圧倒的に差がある場合、やる理由がない、何でそんなことをやっているのか、とにかく、見ていて気分が悪いと思うときは、何かむかついたと入っていくときがある。見ていて、腹が立つと入っていくときがありますが、加減は難しい。それをやっているときには、大人という力を使うから・・・。
**************************************
大人は、子どもに対して力を使うときは、ちゃんと考えをもっておかないと結構あぶない!
それって、大人勝手じゃない???
**************************************
大人は子どもに対して力を使うときは、ちゃんと考えを持っておかないと結構危ない。こちらは、子どもと一緒に遊ぶと思っていても、子どもから見たら、間違いなく大人。同じ友だちとはいかない。大人が何をするかというのは、子どもに影響力は大きい。こどもにとって、プラスの影響かマイナスの影響なのか、大人側は振り返りをもっていないと難しいことが起こる。
リードする中には、誘い出すということがある。指導者ではなく、子どもがもっともっと遊びたいと思えるようにさせるように思うとプレーリーダーの本質に近づく今までの育てられてきた大人は指導者だと思う。指導者は、大人の側が指導する内容を決めるわけ。やっていいこととやっていけないことをきめる。社会で生きていくわけなので、いろんな背景があり、きちんとそれを教えて、それを守らせるようにできるようにする。ちゃんと子どもに対してできるようにすると優秀な指導者と云われる。青少年の健全育成とは、そういうこと。大人が子どもを指導する。つまり、大人社会を背景にして、子どもに向かって、大人社会を代表してものを言うというのが従来の大人のイメージなんです。
*************************************
大人がいて、もっと遊び場をおもしろい遊び場にしようとすると、
子どもがやりたいことをやらせてやろうよ!
*************************************
ところが、さっき言ったように、子どもの遊び場に大人がいるのは、下手するとつまらない。大人がいて、もっと遊び場をおもしろい遊び場にしようとすると、どういうスタンスをとらないといけないかというと、子どもがやりたいことをやらせてやろうよと。そのスタンス。そうすると、全然視点が違ってくる。つまり、公園に穴掘っていけないとすると、指導した人間が怒られ、子どもが穴を掘ってしまた。ところが、無駄な穴をほったことで、いろんな穴が出てくる。公園課からは、穴をはやく埋めてくれと話がでてくる。また、火を焚いたりすると、何時までに消してくれと話になる。穴掘りをすると斜面なので、ホースで水を流すと川ができて、もうとまらない。支流をつくり、橋をかけ、どんどん遊びが進展していく。そうすると、公園をそうしてほしくない側からすると、川を埋めてほしい、ダムを埋めてほしいなどいっぱい来る。だから、僕は、プレーパークに来た1年のうち、3ヶ月くらいは、公園の管理事務所から、午後3時くらいから、プレーパークの天野さん、至急管理事務所に来て下さいと管理事務所に呼び出され、いつ川を埋めてくれるのとか、いつまでに火を消してくれとか言われる。言われるたびに、子どもは楽しそうなんですよねというわけです。でも、公園に作られても困るといわれ、子どもにも伝えるが、見ているこっちも楽しいから、子どもには伝わっていない。そんな感じで、やり取りをしていた。しだいにあきらめていった。
**********************************
子どもがやりたいといっていることを、なぜ、やってはいけないの?
やっちゃだめより
どうすればやれるんだを考える。その発想!!!
**********************************
つまり、子どもがやりたいといっていることをなぜ、やっていけないというの。それを考えると、公園に苦情が出てくるというが見えてきた。例えば、暗くなったときに穴があって、人が落ちたらどうするんだと話があった。でも、人が落ちるのが困るんだったら、まわりに杭を立てて落ちないようにしたらいいだけの話で、そうしますよと話をするが、ダメ。やっちゃダメだという理由が取り除けるんであれば、やっちゃダメだというんではなく、どうしたら、やれるんだと考える。やっちゃダメだということに力をかけるんだったら、どうすればやれるんだを考える方に力をかけていく。その発想だったんです。そうすると、見ていく方向性が逆なんです。
**************************************
子どもの価値観から大人社会を見る!
**************************************
大人の価値観を子どもに向かって言うんではなくて、子どもの価値観から大人社会を見るようになってくるわけです。そうすると、大人がいっていることは、大人勝手だよなと思うです。子どもは、大人の気に触ることをやりたがるというが、あれもうそで、子どもがやりたがることを大人が気に触るんだ。大人がやってほしくないことを禁じたんです。子どもはやりたいからやっていた。昔から。でも、そのときの大人が、嫌がって禁じた。大人が禁じた瞬間から、昔からやっていた行為なのに、ダメなんだ、いけないことなんだ。問題行動を持つ子どもになってしまう。
このあたりは自然が多いから、大丈夫でしょうが、世田谷では、住宅街を歩いていると、雑草なんかはない。例えば、子どもは花をみたら、どうしますか。積んで、花飾りしたり、色水遊びしたりとか、ママゴトで刻んだり、いろんなことをやった。それを積んで、さらに遊びに使うといいが、ただ、棒をもって、花を飛ばして遊んだりもした。無為な殺生もした。花をみたら、摘むたいと思うのは、昔から。小動物を持ってきて、飼うつもりで、殺してしまったりとか、最初から殺してしまったりとか。あり地獄を埋めてしまったりなど、いろんなことをやるわけ。そんなことをやって、命というのは、昔から奪っていた。都市化が進展してくると、世田谷では花はいっぱいあるが、だけど、昔と同じように花をみて、摘みたいと思って、3才の子がお母さんの誕生日に近所から花を摘んできて、花飾りを作って、「お母さんお誕生日おめでとう」といわれたら、最初に一言は、「あんそれどこからとってきたの。」と話をせざるをえない。
*******************************
大人勝手の見立てのいいまち
それは、子どもの住みいいまちとは違う!
*******************************
つまり、大人がきちんと植えた花は誰かのもの。それを採ってきたら・・・。子どもはそれはわからない。ある年齢になればわかるが、わかってもそうだが、花をみれば摘みたくなる。昔からやっていたこと。でも、摘んでいい花は大人は残さなかった。むしろ、そういうものはじゃまな草として、取り除いてきた。つまり、大人勝手だよな。大人勝手の見立てのいいまちを作って、でも、それは子どもの住みいいまちとは違う。花を摘んでもいいというまちを再現したら、問題が起こる。その問題を誰が生んだのかいう話。摘んでいい花を残さなかった大人の問題ではないか。子どもの問題なのか。
つづく。次は、『子どもの問題なのか大人の見方の問題なのか』です。
第4回目は、「指導者ではなく、遊び心を誘い出す」です。
冒険遊び場・講演会 「遊びは生きる力だ!」より、
意地悪というのは子どもの遊びにはつき物。ちょっとした意地悪はつきもの。いじめという言葉は、意地悪の境目は難しいかもしれない。で、子どもの同士の間では意地悪は普通に起こるが、力関係を噴出し起こりうる。
意地悪の範囲は、やはり、子どもの中にあっては、それも仕方のない関係、必要とまで言いがたいが、仕方のない関係。それは、現実として受け入れないと行かない関係。そこのところに大人がしゃしゃりでてはいけないと思うが、これは、いじめであると思うものは。例えば、僕自身が判断するのは、片方が抵抗する気力がない、感じがない、一方的にやり続けている場合、人数的に、力関係で圧倒的に差がある場合、やる理由がない、何でそんなことをやっているのか、とにかく、見ていて気分が悪いと思うときは、何かむかついたと入っていくときがある。見ていて、腹が立つと入っていくときがありますが、加減は難しい。それをやっているときには、大人という力を使うから・・・。
**************************************
大人は、子どもに対して力を使うときは、ちゃんと考えをもっておかないと結構あぶない!
それって、大人勝手じゃない???
**************************************
大人は子どもに対して力を使うときは、ちゃんと考えを持っておかないと結構危ない。こちらは、子どもと一緒に遊ぶと思っていても、子どもから見たら、間違いなく大人。同じ友だちとはいかない。大人が何をするかというのは、子どもに影響力は大きい。こどもにとって、プラスの影響かマイナスの影響なのか、大人側は振り返りをもっていないと難しいことが起こる。
リードする中には、誘い出すということがある。指導者ではなく、子どもがもっともっと遊びたいと思えるようにさせるように思うとプレーリーダーの本質に近づく今までの育てられてきた大人は指導者だと思う。指導者は、大人の側が指導する内容を決めるわけ。やっていいこととやっていけないことをきめる。社会で生きていくわけなので、いろんな背景があり、きちんとそれを教えて、それを守らせるようにできるようにする。ちゃんと子どもに対してできるようにすると優秀な指導者と云われる。青少年の健全育成とは、そういうこと。大人が子どもを指導する。つまり、大人社会を背景にして、子どもに向かって、大人社会を代表してものを言うというのが従来の大人のイメージなんです。
*************************************
大人がいて、もっと遊び場をおもしろい遊び場にしようとすると、
子どもがやりたいことをやらせてやろうよ!
*************************************
ところが、さっき言ったように、子どもの遊び場に大人がいるのは、下手するとつまらない。大人がいて、もっと遊び場をおもしろい遊び場にしようとすると、どういうスタンスをとらないといけないかというと、子どもがやりたいことをやらせてやろうよと。そのスタンス。そうすると、全然視点が違ってくる。つまり、公園に穴掘っていけないとすると、指導した人間が怒られ、子どもが穴を掘ってしまた。ところが、無駄な穴をほったことで、いろんな穴が出てくる。公園課からは、穴をはやく埋めてくれと話がでてくる。また、火を焚いたりすると、何時までに消してくれと話になる。穴掘りをすると斜面なので、ホースで水を流すと川ができて、もうとまらない。支流をつくり、橋をかけ、どんどん遊びが進展していく。そうすると、公園をそうしてほしくない側からすると、川を埋めてほしい、ダムを埋めてほしいなどいっぱい来る。だから、僕は、プレーパークに来た1年のうち、3ヶ月くらいは、公園の管理事務所から、午後3時くらいから、プレーパークの天野さん、至急管理事務所に来て下さいと管理事務所に呼び出され、いつ川を埋めてくれるのとか、いつまでに火を消してくれとか言われる。言われるたびに、子どもは楽しそうなんですよねというわけです。でも、公園に作られても困るといわれ、子どもにも伝えるが、見ているこっちも楽しいから、子どもには伝わっていない。そんな感じで、やり取りをしていた。しだいにあきらめていった。
**********************************
子どもがやりたいといっていることを、なぜ、やってはいけないの?
やっちゃだめより
どうすればやれるんだを考える。その発想!!!
**********************************
つまり、子どもがやりたいといっていることをなぜ、やっていけないというの。それを考えると、公園に苦情が出てくるというが見えてきた。例えば、暗くなったときに穴があって、人が落ちたらどうするんだと話があった。でも、人が落ちるのが困るんだったら、まわりに杭を立てて落ちないようにしたらいいだけの話で、そうしますよと話をするが、ダメ。やっちゃダメだという理由が取り除けるんであれば、やっちゃダメだというんではなく、どうしたら、やれるんだと考える。やっちゃダメだということに力をかけるんだったら、どうすればやれるんだを考える方に力をかけていく。その発想だったんです。そうすると、見ていく方向性が逆なんです。
**************************************
子どもの価値観から大人社会を見る!
**************************************
大人の価値観を子どもに向かって言うんではなくて、子どもの価値観から大人社会を見るようになってくるわけです。そうすると、大人がいっていることは、大人勝手だよなと思うです。子どもは、大人の気に触ることをやりたがるというが、あれもうそで、子どもがやりたがることを大人が気に触るんだ。大人がやってほしくないことを禁じたんです。子どもはやりたいからやっていた。昔から。でも、そのときの大人が、嫌がって禁じた。大人が禁じた瞬間から、昔からやっていた行為なのに、ダメなんだ、いけないことなんだ。問題行動を持つ子どもになってしまう。
このあたりは自然が多いから、大丈夫でしょうが、世田谷では、住宅街を歩いていると、雑草なんかはない。例えば、子どもは花をみたら、どうしますか。積んで、花飾りしたり、色水遊びしたりとか、ママゴトで刻んだり、いろんなことをやった。それを積んで、さらに遊びに使うといいが、ただ、棒をもって、花を飛ばして遊んだりもした。無為な殺生もした。花をみたら、摘むたいと思うのは、昔から。小動物を持ってきて、飼うつもりで、殺してしまったりとか、最初から殺してしまったりとか。あり地獄を埋めてしまったりなど、いろんなことをやるわけ。そんなことをやって、命というのは、昔から奪っていた。都市化が進展してくると、世田谷では花はいっぱいあるが、だけど、昔と同じように花をみて、摘みたいと思って、3才の子がお母さんの誕生日に近所から花を摘んできて、花飾りを作って、「お母さんお誕生日おめでとう」といわれたら、最初に一言は、「あんそれどこからとってきたの。」と話をせざるをえない。
*******************************
大人勝手の見立てのいいまち
それは、子どもの住みいいまちとは違う!
*******************************
つまり、大人がきちんと植えた花は誰かのもの。それを採ってきたら・・・。子どもはそれはわからない。ある年齢になればわかるが、わかってもそうだが、花をみれば摘みたくなる。昔からやっていたこと。でも、摘んでいい花は大人は残さなかった。むしろ、そういうものはじゃまな草として、取り除いてきた。つまり、大人勝手だよな。大人勝手の見立てのいいまちを作って、でも、それは子どもの住みいいまちとは違う。花を摘んでもいいというまちを再現したら、問題が起こる。その問題を誰が生んだのかいう話。摘んでいい花を残さなかった大人の問題ではないか。子どもの問題なのか。
つづく。次は、『子どもの問題なのか大人の見方の問題なのか』です。
Posted by
八日市に冒険遊び場を作る会
at
23:24
│Comments(
0
) │
遊育講演会 報告